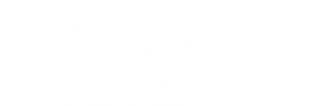植物の葉っぱを眺めていると、その形の多様さに驚かされます。丸い葉、ギザギザの葉、そしてときには針のような葉も。こうした違いには、実はそれぞれ意味があります。
例えば針葉樹。モミやマツのように細くとがった葉は、寒冷地での生活に適応した結果です。積もった雪の重みに枝が折れないよう、雪を滑り落としやすい細い葉を持ち、冬の厳しさをしなやかにしのいでいるのです。
一方、熱帯の植物には、大きくて薄い葉を持つものがたくさんあります。たとえばモンステラやバナナの葉。広い面積で日光をたっぷり受け、光合成を効率よく行うための形です。また葉に切れ込みが入っているのは、風の通り道を作ってダメージを防ぐためとも言われています。
乾燥地に育つ植物たちはというと、また戦略が異なります。アガベやユーフォルビアのように厚みのある葉を持ち、水分をしっかり蓄える構造になっていたり、葉を退化させトゲのようにしてしまったサボテンも。葉からの蒸散を最小限に抑える知恵です。
つまり、葉っぱの形には、環境への適応という”理由”が詰まっているのです。光を求め、風や雪に耐え、乾きやすい土地でも生きるために、植物たちはそれぞれの「機能美」をまとっています。
何気なく眺めている葉のひとつひとつに、静かなる戦略と、たしかな生きる力が隠されているのかもしれません。